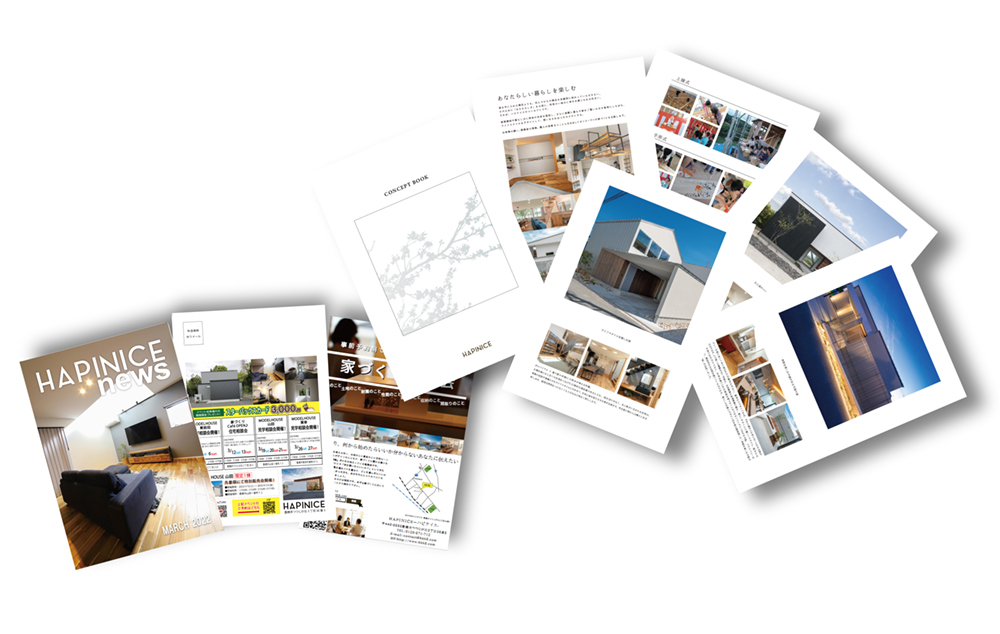2025.08.26
木造住宅でも耐震性は大丈夫?構造の工夫で安心できる家づくり

こんにちは!ハピナイス(HAPINICE)です。
「木造住宅って、地震のときに不安…」「鉄骨やRC造のほうが安心じゃない?」そんな疑問や不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか?
この記事では、木造住宅の耐震性について正しく理解するために、構造の仕組みや耐震等級、耐震性を高める工夫について詳しく解説します。
さらに、ハピナイスが実際に取り入れている耐震性への取り組みや設計事例もご紹介します。
この記事を読むことで、木造住宅でも安心して暮らせる根拠や、注文住宅で地震対策を強化するポイントが分かります。
これからマイホームを建てたいと考えている、子育て世代のご家族はぜひ最後まで読んでみてください!
木造住宅の耐震性は構造次第で大きく変わる

「木造=弱い」というイメージは今や過去のもの。現在の木造住宅は、建築基準法の厳格な基準をクリアし、接合部の金物補強や耐力壁の配置など設計次第で、鉄骨造と同等の耐震性を持つことも可能です。
たとえば、木造住宅に使われる構造用合板や接合金物は、地震時の力を分散・吸収する設計が施されており、揺れによる損傷を最小限に抑えます。また、柱や梁が一定間隔で均等に配置されることで、建物全体がバランスよく揺れるため倒壊リスクが低くなります。
ハピナイスの木造住宅でも、耐震等級3を標準とし、大地震でも家族の命と財産を守れる住宅を目指しています。
〈参考〉
耐震等級1 建築基準法における最低限の耐震性で、「震度6強〜7の地震でも倒壊しない」レベル。
耐震等級2・3 1の1.25倍〜1.5倍の耐震強度を持つとされ、学校や消防署など公共施設でも採用されるレベル
木造住宅の耐震性を高める構造の工夫

木造住宅でも、設計と構造次第で高い耐震性を実現できます。ここでは、具体的な工夫について紹介します。
耐力壁とバランス配置で揺れに強くする
耐震性を高める基本は「耐力壁」の配置です。
耐力壁とは、地震や強風の揺れに建物が倒れないように支える壁のこと。建物の骨組みをしっかり支える柱のようなイメージです。
例えば、家の南側に大きな窓をたくさんつけてしまうと、壁のバランスが偏ってしまい、地震に弱くなってしまうことがあります。逆に壁の配置をバランスよく設計すると、建物がねじれにくく、揺れにも強くなります。
ハピナイスでは、耐力壁をどこに置くかを建物ごとに計算し、デザインと耐震性の両立を実現しています。また、壁の強さを高める「構造用合板」や「筋交い」という補強材を使うことで、コンパクトな家でも強い構造を作ることが可能です。
自分自身で簡易にチェックする場合には
- 大きな窓や吹き抜けの位置で壁が減りすぎていないか
- 家の形が極端に偏っていないか
- 設計段階で耐震等級や耐力壁の配置を確認できるか
こうした点を押さえるだけでも、地震に強い木造住宅を選ぶ目安になります。
接合金物による構造補強
木造住宅は、柱や梁が“接合部”で組まれているため、その接合部分の強度が建物の耐震性に直結します。
ハピナイスでは、伝統的な「木造軸組み工法」と、ドリフトピンという専用金物を使用して柱や梁を接合する「ピン工法」のハイブリッド工法を採用し、従来の木組みよりも精度が高く強固な接合を実現しています。
これにより、地震時の揺れに対する変形を最小限に抑え、構造体の損傷を防ぎます。
基礎構造の強さが耐震性を左右する
そして家の耐震性を語るうえで欠かせないのが「基礎構造」です。基礎は建物全体を支える土台の部分であり、地震の揺れの大部分を最初に受け止める重要な役割を担っています。基礎がしっかりしていなければ、どれだけ上部構造を強くしても十分な耐震性は確保できません。
木造住宅でよく使われる基礎には大きく分けて 「ベタ基礎」 と 「布基礎」 の2種類があります。
- ベタ基礎
建物の床下全体を鉄筋コンクリートで覆う方法です。建物の荷重や地震の力を面で受け止めるため、不同沈下(地盤の部分的な沈み込み)が起きにくく、耐震性や耐久性に優れています。シロアリや湿気の侵入も防ぎやすい点がメリットです。 - 布基礎
建物の外周部や主要な部分に帯状に基礎を配置する方法です。従来からある工法で、コストを抑えられる点が特徴。ただし、地盤の状態や設計によってはベタ基礎に比べて耐震性が劣るケースもあります。
ハピナイスでは、基礎全面に鉄筋を施し、厚さ150mmの土間コンクリートを打つベタ基礎を標準としています。しっかりとした基礎があるからこそ、大地震の際も建物全体が安定しやすく、家族を守ることができるのです。
でもやっぱり「鉄骨の方が強いのでは?」

「耐震性=鉄骨の方が優れている」というイメージを持つ方も多いかもしれません。たしかに鉄骨は部材自体が強く、大空間や高層建築に適しています。しかし、住宅レベルの建物においては、木造でも設計と施工の工夫次第で同等以上の耐震性を実現できます。
木造住宅は、軽量であることが大きな強み。建物が軽いほど地震のエネルギーを受ける量も少なくなるため、揺れに強い構造をつくりやすいのです。
また、最新の木造住宅は耐震等級3を取得することで、鉄骨造と同等の地震安全性を備えています。
さらに、木材はしなやかで弾力があるため、地震の衝撃を吸収・分散しやすい性質も持っています。つまり、「鉄骨だから安心」「木造だから不安」という単純な比較ではなく、どの構造でも設計と施工の品質が耐震性を左右するのです。
まとめ
木造住宅は、適切な設計と構造上の工夫によって、十分な耐震性を確保できます。
耐力壁の配置、剛床工法、金物補強、そして構造計算といった各要素を組み合わせることで、家族を守る強い住まいが実現できます。
ハピナイスでは、デザイン性と耐震性を両立させた安心の木造住宅を提案しています。「おしゃれな家にしたいけど、安全性も妥協したくない」そんなご家族にこそ、ハピナイスの注文住宅はぴったりです。
地震に強いデザイン住宅を探しているご家族は、是非この記事を参考にしてくださいね!
ハピナイスでは、豊橋・豊川・田原・蒲郡・新城・湖西エリア周辺でお客様にピッタリのデザイン性の高い注文住宅を提案しています。
東三河エリア周辺のお家づくりはHAPINICEにお任せください!
ハピナイスで行っている構造と性能についての取り組みを詳しくご覧になりたい方はこちら
「家づくりの想い ABILITY 構造と性能について」
シリーズ「住まいの耐震」コラム
❶耐震とは?初心者でもわかる基礎知識と重要性
❷耐震等級とは?1~3の違いと意味を徹底解説
❸【保存版】耐震構造の種類と特徴まとめ
❹住宅の耐震診断とは?流れ・費用・注意点を解説
❺耐震基準はいつから変わった?1981年との違いとは
❻耐震性が不安な家を見分けるチェックポイント
❼木造住宅でも耐震性は大丈夫?構造の工夫で安心できる家づくり(この記事です)
CATEGORIES
- 動画で学ぶ (301)
- 家づくりのこと (438)
- 間取り (10)
- 平屋 (44)
- 耐震 (32)
- 電気代0円住宅(太陽光/蓄電池/ZEH/高気密高断熱/省エネ) (29)
- サウナのある家 (18)
- ガレージのある家 (22)
- ペットと暮らす家 (17)
- 収納 (2)
- キッチン (27)
- 洗面・バス・トイレ (26)
- リビング (39)
- 玄関 (23)
- 階段ホール・廊下 (24)
- 外観 (35)
- お金・住宅ローン (103)
- スタッフブログ (1,401)
- イベントレポート (97)
- 撮影レポート (13)
- 現場レポート (14)
- MODEL HOUSE – 東幸 – (46)
- MODEL HOUSE – 菰口 – (69)
- 林 拓未 (1,073)
- コーディネーター田中やよい (130)
- 広報 小林 紗矢香 (37)
- 広報 尾上 愛斗奈 (15)
- 保育 河原 愛 (22)
- 総務 水野 瞳 (104)
- 総務 戸塚 里美 (130)
- コラム (38)
- プライベートのこと (76)
- 趣の空間のこと (45)
- その他 (783)
- アーカイブ (1,314)